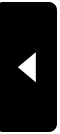2010年05月06日
檜洞丸 後編
またしても 雨にたたられたワンゲル部なんですが
やっと山頂に着き お昼ご飯となりました。
立ち止まると
汗をかいた体が冷え 雨と風で、より一層寒くななります
僕は山伏の教訓があるので、寒い中Tシャツを替えたのだが
女子は そうもいかない。
コンロでお湯を沸かし、思い思いに味噌汁で暖をとりました
その間に 雲が早く動き出しガスもとれて視界も良くなってきました
相変わらず、周りの山などは見えませんが少しは気が晴れてきます。
いつまでも、じっとしてると寒いので出発です。
雨も ほとんど止み視界も良くなってます。

これならいいですね!
朝来た道との分岐に来て、迷いました。
最短で降りるには この道
しかし、天候も良くなったし このままいいとこなしで下るのはもったいない...
迷った挙句、当初の予定通り
真っすぐ稜線を進む事にします。
ここから先は、アップダウンもありながら緩く下っていく快適な道

時折、ガスも晴れて下界が見渡せます
今まで 高度感が分からなかったけど
これで登った苦労が報われます
相変わらずのガスの中を 緩く山腹を巻く道にさしかかると
鹿です!

分かりにくいですけど 写真中央
白いお尻が写っています。
ガスの効果か とても神秘的に見えました
しばらく歩くと

バンザイの木!
ここで みんなで写真を撮りました
稜線との分岐点である石棚山に到着
しばし休憩です。
みんなの顔も 寒~い山頂に比べ晴れてきた
頭上には 蕾が膨らんだばかりの桜の木
まだ稜線上は冬なんですねぇ
ここから箒橋に向けての下りなんだけど
いくつかの小ピークを越えたり、難所をクリアしたりと侮れない道が続きます

ようやく空も 青空を見せ始め
なかなかにシンドかった山行のフィナーレを飾るかのようです
ぐんぐんと高度を下げて 沢の音も近づいてくると
ようやく待ち焦がれた 新緑が現れました

う~ん 目に眩しい

あとは10分も 沢沿いの快適な道を行けば
箒橋に到着です。
ようやく、自分としても
本来の目的である「新緑に親しむ」という目的を達成した感があり
一安心。。
それにしても ちょっと早かったですねぇ
5月の半ばから 後半にかけてでしょうか。。
きっと その頃には
稜線上のブナの新緑とシロヤシオが楽しめると思います
その後の 筋肉痛と共に
今回の山行は充実したものとなりました
丹沢も久し振りだったし....
ワンゲル部も一歩前進?かな
やっと山頂に着き お昼ご飯となりました。
立ち止まると
汗をかいた体が冷え 雨と風で、より一層寒くななります
僕は山伏の教訓があるので、寒い中Tシャツを替えたのだが
女子は そうもいかない。
コンロでお湯を沸かし、思い思いに味噌汁で暖をとりました
その間に 雲が早く動き出しガスもとれて視界も良くなってきました
相変わらず、周りの山などは見えませんが少しは気が晴れてきます。
いつまでも、じっとしてると寒いので出発です。
雨も ほとんど止み視界も良くなってます。

これならいいですね!
朝来た道との分岐に来て、迷いました。
最短で降りるには この道
しかし、天候も良くなったし このままいいとこなしで下るのはもったいない...
迷った挙句、当初の予定通り
真っすぐ稜線を進む事にします。
ここから先は、アップダウンもありながら緩く下っていく快適な道

時折、ガスも晴れて下界が見渡せます
今まで 高度感が分からなかったけど
これで登った苦労が報われます
相変わらずのガスの中を 緩く山腹を巻く道にさしかかると
鹿です!

分かりにくいですけど 写真中央
白いお尻が写っています。
ガスの効果か とても神秘的に見えました

しばらく歩くと

バンザイの木!
ここで みんなで写真を撮りました
稜線との分岐点である石棚山に到着
しばし休憩です。
みんなの顔も 寒~い山頂に比べ晴れてきた
頭上には 蕾が膨らんだばかりの桜の木
まだ稜線上は冬なんですねぇ
ここから箒橋に向けての下りなんだけど
いくつかの小ピークを越えたり、難所をクリアしたりと侮れない道が続きます

ようやく空も 青空を見せ始め
なかなかにシンドかった山行のフィナーレを飾るかのようです
ぐんぐんと高度を下げて 沢の音も近づいてくると
ようやく待ち焦がれた 新緑が現れました

う~ん 目に眩しい

あとは10分も 沢沿いの快適な道を行けば
箒橋に到着です。
ようやく、自分としても
本来の目的である「新緑に親しむ」という目的を達成した感があり
一安心。。
それにしても ちょっと早かったですねぇ
5月の半ばから 後半にかけてでしょうか。。
きっと その頃には
稜線上のブナの新緑とシロヤシオが楽しめると思います

その後の 筋肉痛と共に
今回の山行は充実したものとなりました
丹沢も久し振りだったし....
ワンゲル部も一歩前進?かな

2010年05月01日
ワンゲル部 3回目 檜洞丸
2カ月ぶりのワンゲル部の山行です。
4月だし、そろそろ中級編にレベルアップして
手応えのある山に行こうと決めてました。
ちょっと早いと思ったけど
新緑を求めてブナの多い山域、西丹沢(神奈川県)の檜洞丸を目指します。
朝6時集合でバイパス、東名と乗り継ぎ
御殿場に降りたのが7時半
GW初日で朝から車もでています。
246にはいり、神奈川方面に向って暫く行くと
丹沢湖への入口があります
左折して北進していくと
にわかにあたりは暗くなって行き
先行きが不安になってきます。
天気予報では、昼まで曇り
お昼頃、にわか雨がありそう。。
なんとかご飯を食べるまでもってくれるといいが
西丹沢自然教室に車を置き
身支度を整えると
ここで登山届を提出します
地図には、最近の山の情報が書かれ
簡単な注意事項を聞きます。
人気な山域とあって、ちゃんとしてます!
さぁ やっと出発
車道を10分程進むと
沢の横に作られた登山道が出てきます

なぜか 皆それぞれピース。。
この山域は 植林されている処が少なく
最初から自然林の中を登っていきます。
萌えだしたばかりの緑や、山桜のハラハラする様を見ながら
低い尾根をのっこし ゴーラ沢沿いの水平道にでました

係の人に聞いていたように増水しています。
いつもなら、飛び石伝いに渡れる川も
これでは、ちょっと無理
靴を脱いで渡渉することにします。
二人一組で、少しづつ進んだんだけど
川の水が予想以上に冷たい!

川幅があって渡渉が長かったら、大変でした
体制を整えて、本日のメインイベント
ツツジコースの登りにかかります

浸食されて 木の根が露出した登山道は
所々に悪場を作り、鎖をたよりに登らなければならないところがあります。
やはり 名のとおり
ツツジが多いルート
たくさんのツツジが出迎えてくれました

最初の急登を過ぎたあたりから
次第に雨が落ち始め
上気した体には 心地良かったんだけど
段々、洒落にならない量になってきます
そのうち 風も出始めて
ニュースの「全国的荒れ模様、時折強い風が吹くでしょう」
という言葉を思い出しました
高度を上げれば上げる程
緑の量は減り、視界も無くなってきます
以前、訪れた時に見たシロヤシオも
まだ、全然早いようで どこにあるのかすらも分かりません
また、視界がない為
目的の稜線も、近づいていることすら分からず
ただ、やみくもに足を運んで風と雨をしのぎながら歩をすすめていくしかありません
木の階段が出始めると、稜線は近い
いくつかの滑りやすい階段を過ぎて
稜線に到着
ここからは 頂上に向けてなだらかな木道が続く
木道の周りには
バイケイソウが芽を出していて
まだ春早い 様相です
ここも時期なら ブナの新緑を楽しめる素敵な道なのだが
ちょっと早かった
雲が にわかに動き出した頃
小広い山頂に到着

ふぅ~やっと着いたねぇ~
雨と強風の中 よく頑張りました!
ということで、
雨と風の 試練の前篇は終わりです
天候が回復して 鹿が現れる後編に続きます
4月だし、そろそろ中級編にレベルアップして
手応えのある山に行こうと決めてました。
ちょっと早いと思ったけど
新緑を求めてブナの多い山域、西丹沢(神奈川県)の檜洞丸を目指します。
朝6時集合でバイパス、東名と乗り継ぎ
御殿場に降りたのが7時半
GW初日で朝から車もでています。
246にはいり、神奈川方面に向って暫く行くと
丹沢湖への入口があります
左折して北進していくと
にわかにあたりは暗くなって行き
先行きが不安になってきます。
天気予報では、昼まで曇り
お昼頃、にわか雨がありそう。。
なんとかご飯を食べるまでもってくれるといいが
西丹沢自然教室に車を置き
身支度を整えると
ここで登山届を提出します
地図には、最近の山の情報が書かれ
簡単な注意事項を聞きます。
人気な山域とあって、ちゃんとしてます!
さぁ やっと出発
車道を10分程進むと
沢の横に作られた登山道が出てきます

なぜか 皆それぞれピース。。
この山域は 植林されている処が少なく
最初から自然林の中を登っていきます。
萌えだしたばかりの緑や、山桜のハラハラする様を見ながら
低い尾根をのっこし ゴーラ沢沿いの水平道にでました

係の人に聞いていたように増水しています。
いつもなら、飛び石伝いに渡れる川も
これでは、ちょっと無理
靴を脱いで渡渉することにします。
二人一組で、少しづつ進んだんだけど
川の水が予想以上に冷たい!

川幅があって渡渉が長かったら、大変でした
体制を整えて、本日のメインイベント
ツツジコースの登りにかかります

浸食されて 木の根が露出した登山道は
所々に悪場を作り、鎖をたよりに登らなければならないところがあります。
やはり 名のとおり
ツツジが多いルート
たくさんのツツジが出迎えてくれました

最初の急登を過ぎたあたりから
次第に雨が落ち始め
上気した体には 心地良かったんだけど
段々、洒落にならない量になってきます
そのうち 風も出始めて
ニュースの「全国的荒れ模様、時折強い風が吹くでしょう」
という言葉を思い出しました
高度を上げれば上げる程
緑の量は減り、視界も無くなってきます
以前、訪れた時に見たシロヤシオも
まだ、全然早いようで どこにあるのかすらも分かりません
また、視界がない為
目的の稜線も、近づいていることすら分からず
ただ、やみくもに足を運んで風と雨をしのぎながら歩をすすめていくしかありません
木の階段が出始めると、稜線は近い
いくつかの滑りやすい階段を過ぎて
稜線に到着
ここからは 頂上に向けてなだらかな木道が続く
木道の周りには
バイケイソウが芽を出していて
まだ春早い 様相です
ここも時期なら ブナの新緑を楽しめる素敵な道なのだが
ちょっと早かった
雲が にわかに動き出した頃
小広い山頂に到着

ふぅ~やっと着いたねぇ~
雨と強風の中 よく頑張りました!
ということで、
雨と風の 試練の前篇は終わりです
天候が回復して 鹿が現れる後編に続きます
2010年03月24日
静岡の百山
あ~明日も雨だぁ~σ(TεT;)
1か月ぶりに山に行こうと思ってたけど、雨の予報....
仕方ないので机上登山だぁ~
100名山という言葉を聞かれた事がある方もいらっしゃるかと思いますが
北海道の利尻島から鹿児島の屋久島までの名山を深田久弥氏が100山にまとめて
本に書かれたのが始まりで、ちょっとしたブームになりました。
こうしたピークハント的な山登りが批判されることもありますが、
ある程度の目標と、知らない場所に行くモディベーションになってるので
僕は肯定的です。
でも、時間と経済的にとても無理なので
まぁ、一生の間にいければなぁー とゆる~く考えています。
(ちなみに、現在10座程度という、しょぼ~い記録です)
そこで、身近な目標はないものかと
こんな本を目標にしだして

結構、行ってるのだが同じ山を何度も登ってるので一向に数が増えていきません
(ちなみに先日登った山伏は7回登ってます)
そのうちに山梨百名山というのを知り
こちらも、細々と初めています
「静岡にもないなのかなぁ?」と思ってたら
先日、図書館で見つけました

あぁ~やっぱあるんだぁ~
こういうのを見つけてしまうと
元来、好きな事にはマニアックになる傾向がある自分は
Exelでまとめて、山行記録も書けるように作りたくなります。。
この本の中身は、歴史や資料的な部分に誌面をさかれており
コースガイド的でないのも嬉しいところです
こういう予備知識が山行を楽しく深くしてくれるんですねぇ
まぁ あんまり肩肘はらずに
この本を目安や目標にしながら静岡百山を楽しんでいこうかと思っています
ちなみにネットで検索すると
かなり百名山関係はヒットします
なかには、スゴイつわものもいます
ご興味のある方は、検索してみてください
1か月ぶりに山に行こうと思ってたけど、雨の予報....
仕方ないので机上登山だぁ~
100名山という言葉を聞かれた事がある方もいらっしゃるかと思いますが
北海道の利尻島から鹿児島の屋久島までの名山を深田久弥氏が100山にまとめて
本に書かれたのが始まりで、ちょっとしたブームになりました。
こうしたピークハント的な山登りが批判されることもありますが、
ある程度の目標と、知らない場所に行くモディベーションになってるので
僕は肯定的です。
でも、時間と経済的にとても無理なので
まぁ、一生の間にいければなぁー とゆる~く考えています。
(ちなみに、現在10座程度という、しょぼ~い記録です)
そこで、身近な目標はないものかと
こんな本を目標にしだして

結構、行ってるのだが同じ山を何度も登ってるので一向に数が増えていきません
(ちなみに先日登った山伏は7回登ってます)
そのうちに山梨百名山というのを知り
こちらも、細々と初めています
「静岡にもないなのかなぁ?」と思ってたら
先日、図書館で見つけました

あぁ~やっぱあるんだぁ~
こういうのを見つけてしまうと
元来、好きな事にはマニアックになる傾向がある自分は
Exelでまとめて、山行記録も書けるように作りたくなります。。

この本の中身は、歴史や資料的な部分に誌面をさかれており
コースガイド的でないのも嬉しいところです
こういう予備知識が山行を楽しく深くしてくれるんですねぇ
まぁ あんまり肩肘はらずに
この本を目安や目標にしながら静岡百山を楽しんでいこうかと思っています
ちなみにネットで検索すると
かなり百名山関係はヒットします
なかには、スゴイつわものもいます
ご興味のある方は、検索してみてください
2010年03月01日
真富士山 後編
スイマセン....ちょっと間が空きましたが
ワンゲル部の真富士山山行の後編です。
トトロ的な道(部員命名)を下りきると、真富士峠に到着
ここからが高度差 約100mの登り返し。。意外に遠くみえます
歩き始めて まもなく紫の道(これも部員命名)
イワカガミの葉が、この時期は紫色をしていて
緑少ない道に彩りを与えています。。
第一真富士山までのなだらかな道から
少しだけ険しい様相を呈してきます。
深く切れ込んだ谷が登山道の道幅を狭くしているところや
崖に登山道をつくったようなところもあります

僕は、これぐらいが楽しいけど
慣れない部員たちには大変そうです。
ちょっとした樹幹の切れ間から南アルプス方面が見渡せました

ん~いい天気!
いくつか、ニセ頂上を通り過ぎ第二真富士山に到着

さぁ お腹も空いたしご飯です!
今日のメニューはキムチ鍋

3人分なのに多すぎ!です。
これでもまだ豆腐が入っていないのです....
疲れた体に ピリ辛キムチ鍋は堪えられない美味しさ!
やっぱ山で食べるご飯は最高です!
これでも お腹一杯なのに締めにそうらーめんも加えて完食。
あ~天気もいいし暖かいし、お腹一杯だし
ここで、しばらく昼寝をしたいなぁ~という気分ですなぁ
まぁそんなことも言ってられないので下山開始
登りで大変だったとこは、下りの方が大変です
足の置き場に注意しながら、難所をクリアすれば
あっという間に下降点の真富士峠。。
真富士峠を下って、行きの分岐であるヲイ平を経由すれば
後は、朝登った道を下るだけです
ちなみに今回のコース

距離5.5㎞、高度差700メートル 往復3時間ぐらい
前回の浜石岳に比べて高度差は変わらないけど、距離は短めです。
それにしても、天気がいいだけで こんなにも気持ちの疲労度が違うのか....
みんなもご機嫌で下山。。
さぁ~打ち上げだぁ~
今回の打ち上げは、浅間さん近くの「あさひ」さん
お風呂もはいり、スッキリして5時半に集合!
ビールに焼き豚、フライ、おでん....
ここで その写真を貼りたいとこなのだが、、無い
「あさひなう」とかTwitterで遊んでいたので写真を保存しておらず。。
お暇な方は ココのほうにいくつかあがっておりますのでソチラをご覧になって頂いて。。
なんとかあったのが この程度

まぁ雰囲気だけ ということで(ちなみにi PhoneアプリのLomoで撮影)。。
閉店の9時半まで盛り上がりましたぁ
やっぱ、いい山だと打ち上げも楽しいー
ワンゲル部の真富士山山行の後編です。
トトロ的な道(部員命名)を下りきると、真富士峠に到着
ここからが高度差 約100mの登り返し。。意外に遠くみえます
歩き始めて まもなく紫の道(これも部員命名)
イワカガミの葉が、この時期は紫色をしていて
緑少ない道に彩りを与えています。。
第一真富士山までのなだらかな道から
少しだけ険しい様相を呈してきます。
深く切れ込んだ谷が登山道の道幅を狭くしているところや
崖に登山道をつくったようなところもあります

僕は、これぐらいが楽しいけど
慣れない部員たちには大変そうです。
ちょっとした樹幹の切れ間から南アルプス方面が見渡せました

ん~いい天気!
いくつか、ニセ頂上を通り過ぎ第二真富士山に到着

さぁ お腹も空いたしご飯です!
今日のメニューはキムチ鍋

3人分なのに多すぎ!です。
これでもまだ豆腐が入っていないのです....
疲れた体に ピリ辛キムチ鍋は堪えられない美味しさ!

やっぱ山で食べるご飯は最高です!
これでも お腹一杯なのに締めにそうらーめんも加えて完食。
あ~天気もいいし暖かいし、お腹一杯だし
ここで、しばらく昼寝をしたいなぁ~という気分ですなぁ

まぁそんなことも言ってられないので下山開始
登りで大変だったとこは、下りの方が大変です
足の置き場に注意しながら、難所をクリアすれば
あっという間に下降点の真富士峠。。
真富士峠を下って、行きの分岐であるヲイ平を経由すれば
後は、朝登った道を下るだけです
ちなみに今回のコース

距離5.5㎞、高度差700メートル 往復3時間ぐらい
前回の浜石岳に比べて高度差は変わらないけど、距離は短めです。
それにしても、天気がいいだけで こんなにも気持ちの疲労度が違うのか....
みんなもご機嫌で下山。。
さぁ~打ち上げだぁ~
今回の打ち上げは、浅間さん近くの「あさひ」さん
お風呂もはいり、スッキリして5時半に集合!
ビールに焼き豚、フライ、おでん....
ここで その写真を貼りたいとこなのだが、、無い

「あさひなう」とかTwitterで遊んでいたので写真を保存しておらず。。
お暇な方は ココのほうにいくつかあがっておりますのでソチラをご覧になって頂いて。。
なんとかあったのが この程度

まぁ雰囲気だけ ということで(ちなみにi PhoneアプリのLomoで撮影)。。
閉店の9時半まで盛り上がりましたぁ
やっぱ、いい山だと打ち上げも楽しいー

2010年02月27日
ワンゲル部第二回山行 真富士山
さて、今回のワンゲル部
先週の雪とかで、散々悩んだ挙句
真富士山にいく事にしました。
予報は、晴れのち曇り
お昼ぐらいまでは、天気が良さそうです
(なんとか、今回は雨をまぬがれた...今回降ったら完全に雨男でした。。。ふぅ~)
8時20分集合で、安倍川を北上です。
近いから、遅めの出発
途中、コンビニで行動食やら水を補給して
平野集落の林道にはいっていきます
ガードレールのない、ちょっと恐い道をいくらか登ると登山口がありました。
「あれ?登山口の看板、黄色じゃなかったっけ?」
地図をみても、沢の脇を登るこの道は、どうやら違う.....
もう少し、車であがってみることにします
5分程 登ってみると。。ありました黄色い看板。。
支度をすませて、9時30分 登山開始です!

登山道にはいってスグ

三椏(みつまた)の群落です
花や緑が少ない、冬の山にポチポツと花芽をつけた姿が可愛いですねぇ
三椏は和紙の原料とされたので、この辺りで和紙が作られていたのでしょうか?
枝が三つに分かれているところから三椏と言われててるようです
今日は晴れているので、木漏れ日も美しい

杉林から、水平道、沢を横切り小尾根に取り付いて数分
最初の目的地 ヲイ平につき小休憩

この子達 ヲイ平(ヲイダイラ)をヲイヘイと思ってたらしい
同じように、真富士山(マフジヤマ)をシンフジサンと読んでいた。。。これからは漢字にルビを振ろう!
ヲイ平からは、杉林を抜け広葉樹帯の急登
落葉して、明るくなった山腹をジグザグに登り高度をかせぎます。
傾斜も緩くなってくると、苔むした石がゴロゴロした場所にでてきました

この辺は、ちょっと雪が残ってたり凍ってたりと緊張させられます
上空を見上げると、飛行機雲

あ~天気がいいと、なんて楽しいんだろう
前回とは雲泥の差です。。
悪場を過ぎ、小尾根を回りこんだら ほどなく稜線です。
このコースは、僕も初めてですが 短時間に景色が変わり
変化があって飽きさせません
稜線上は、広葉樹と照葉樹の明るい道です
冬の低山の楽しみというのは、落葉して明るくなり景色も見えやすいというところですねぇ
ほどなく山頂

今日は、富士山もバッチリ!
いいねぇ~最高!
ひとしきり、景色を満喫して写真を撮ったら
次の目的地、第二真富士山に向かいます

第二真富士山の方が70mほど標高が高いのです。
ここから、一旦 真富士峠まで下って登り返しの行程
*大分、長くなったので このへんで続きにします。
次回「ワンゲル部第二回山行 キムチ鍋&打ち上げ篇(仮)」もお楽しみに!
先週の雪とかで、散々悩んだ挙句
真富士山にいく事にしました。
予報は、晴れのち曇り
お昼ぐらいまでは、天気が良さそうです

(なんとか、今回は雨をまぬがれた...今回降ったら完全に雨男でした。。。ふぅ~)
8時20分集合で、安倍川を北上です。
近いから、遅めの出発
途中、コンビニで行動食やら水を補給して
平野集落の林道にはいっていきます
ガードレールのない、ちょっと恐い道をいくらか登ると登山口がありました。
「あれ?登山口の看板、黄色じゃなかったっけ?」
地図をみても、沢の脇を登るこの道は、どうやら違う.....
もう少し、車であがってみることにします
5分程 登ってみると。。ありました黄色い看板。。
支度をすませて、9時30分 登山開始です!

登山道にはいってスグ

三椏(みつまた)の群落です
花や緑が少ない、冬の山にポチポツと花芽をつけた姿が可愛いですねぇ
三椏は和紙の原料とされたので、この辺りで和紙が作られていたのでしょうか?
枝が三つに分かれているところから三椏と言われててるようです
今日は晴れているので、木漏れ日も美しい

杉林から、水平道、沢を横切り小尾根に取り付いて数分
最初の目的地 ヲイ平につき小休憩

この子達 ヲイ平(ヲイダイラ)をヲイヘイと思ってたらしい

同じように、真富士山(マフジヤマ)をシンフジサンと読んでいた。。。これからは漢字にルビを振ろう!

ヲイ平からは、杉林を抜け広葉樹帯の急登
落葉して、明るくなった山腹をジグザグに登り高度をかせぎます。
傾斜も緩くなってくると、苔むした石がゴロゴロした場所にでてきました

この辺は、ちょっと雪が残ってたり凍ってたりと緊張させられます
上空を見上げると、飛行機雲

あ~天気がいいと、なんて楽しいんだろう
前回とは雲泥の差です。。
悪場を過ぎ、小尾根を回りこんだら ほどなく稜線です。
このコースは、僕も初めてですが 短時間に景色が変わり
変化があって飽きさせません
稜線上は、広葉樹と照葉樹の明るい道です
冬の低山の楽しみというのは、落葉して明るくなり景色も見えやすいというところですねぇ
ほどなく山頂

今日は、富士山もバッチリ!
いいねぇ~最高!
ひとしきり、景色を満喫して写真を撮ったら
次の目的地、第二真富士山に向かいます

第二真富士山の方が70mほど標高が高いのです。
ここから、一旦 真富士峠まで下って登り返しの行程
*大分、長くなったので このへんで続きにします。
次回「ワンゲル部第二回山行 キムチ鍋&打ち上げ篇(仮)」もお楽しみに!
タグ :登山





 Copyright(C)2025/ヴィラデストクイジーヌ ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/ヴィラデストクイジーヌ ALL Rights Reserved